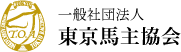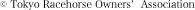東京競馬場の沿革・その1(前史と施設の変遷)
私たち東京馬主協会のホームグラウンド、そして日本を代表する競馬場としても親しまれている東京競馬場。その前身にあたるのが、明治40年に創設された目黒競馬場です。もともとは日本競馬会という主催団体によって設立された歴史を持ち、現在の東京都目黒区下目黒4~6丁目付近に広がっていたこの目黒競馬場は、馬券発売禁止令の発令(明治41年10月)にともない東京近郊の4つの主催団体(東京競馬会、京浜競馬倶楽部、日本競馬会、東京ジョッケー倶楽部)が東京競馬会に合併される形で「東京競馬倶楽部」が誕生(明治43年5月)した際、立地や地勢、施設などの条件からその本拠地に選ばれた経緯があります。馬券の発売が禁止され、政府からのわずかな補助金を頼りに開催が続けられていた時代にも、「景品付き抽選券」を発行するなど様々な工夫を凝らして集客に努めた目黒競馬場の開催には、多い日には3千人に近い観客が詰めかけた記録が残っています。

東京競馬倶楽部が競走を主催していた目黒競馬場
とはいえ、長期間にわたって広大な敷地を必要とする競馬事業に土地問題が絡んでくるのは宿命的な構図といえ、敷地の8割以上を借地で賄っていた目黒競馬場もその例に漏れませんでした。立地条件のよさから競馬場の周辺では宅地化が進み、特に大正12年9月に発生した関東大震災後における東京郊外の急激な発展は地価地代の高騰を呼ぶことにもなりました。これにともない、地元関係者の間では「競馬場の移転」を主張する声が大きくなっていきます。一方の東京競馬倶楽部の側でも、競馬法の施行(大正12年7月)によって馬券の発売が正式に認可されて以降、競馬人気が全国的に隆盛へ向かい、従来の施設では十分な対応が困難になってきたことも受け、「馬の全能力が余すところなく発揮できる」ために必要な広大な馬場を擁する新たな競馬場を建設したいとの機運が高まっていきました。
こうした流れのもと、東京競馬倶楽部副会長兼常務理事の安田伊左衛門は同理事の楠本正敏男爵を伴って、大正14年6月、新競馬場の建設を前提に踏まえた海外視察に旅立ちます。行き先はオーストラリア。長い歴史を持つ欧米諸国ではなく、世界的には競馬の新興国と見なされていた南半球の国を敢えて視察の対象としたのは、レジャーとしての一面を重視しながら発展を遂げつつあった同国の競馬の運営、施行方法、またスタンドの形態等の施設面に、日本の競馬が進むべき道を見出したからでした。
オーストラリアに到着後、主だった競馬場をひと通り巡回した一行は、新たに建設する競馬場の“施設面のモデル”としてウォーウィック競馬場に白羽の矢を立て、その設計図を購入して日本へ持ち帰ります。帰国後、移転の動きはいよいよ本格化し、昭和2年4月には競馬場移転準備に関する委員会が正式に発足。数十ヶ所に及んだ候補地を様々な角度から検討した結果、東京府下北多摩郡府中町南寄りの土地を新競馬場の建設予定地に選定(昭和3年)します。当時の府中町は多磨村、西府村を含めても人口約1万5千人という小さな町で、新宿ー東八王子間の連絡運輸が開始されたばかりとあって「交通至便」ともいえない立地条件でしたが、多摩川水系に支えられた豊富な水と良質の青草に恵まれていたこと、さらに町が一丸となって繰り広げた熱心な招致運動と協力体制が選定の“決め手”となりました。
こうした流れのもと、東京競馬倶楽部副会長兼常務理事の安田伊左衛門は同理事の楠本正敏男爵を伴って、大正14年6月、新競馬場の建設を前提に踏まえた海外視察に旅立ちます。行き先はオーストラリア。長い歴史を持つ欧米諸国ではなく、世界的には競馬の新興国と見なされていた南半球の国を敢えて視察の対象としたのは、レジャーとしての一面を重視しながら発展を遂げつつあった同国の競馬の運営、施行方法、またスタンドの形態等の施設面に、日本の競馬が進むべき道を見出したからでした。
オーストラリアに到着後、主だった競馬場をひと通り巡回した一行は、新たに建設する競馬場の“施設面のモデル”としてウォーウィック競馬場に白羽の矢を立て、その設計図を購入して日本へ持ち帰ります。帰国後、移転の動きはいよいよ本格化し、昭和2年4月には競馬場移転準備に関する委員会が正式に発足。数十ヶ所に及んだ候補地を様々な角度から検討した結果、東京府下北多摩郡府中町南寄りの土地を新競馬場の建設予定地に選定(昭和3年)します。当時の府中町は多磨村、西府村を含めても人口約1万5千人という小さな町で、新宿ー東八王子間の連絡運輸が開始されたばかりとあって「交通至便」ともいえない立地条件でしたが、多摩川水系に支えられた豊富な水と良質の青草に恵まれていたこと、さらに町が一丸となって繰り広げた熱心な招致運動と協力体制が選定の“決め手”となりました。
従来の目黒競馬場の敷地の実に約4倍、約24万坪にも及ぶ広大な用地の買収交渉が一段落し、建設工事に着工されたのは昭和7年3月31日のこと。もともとは田野であった敷地には、先述したウォーウィック競馬場の設計図を下敷きとして、1年余りのうちに広々とした走路と雄大な威容を誇る2つのスタンドが建設され、昭和8年11月8日には竣工式典が盛大に行われました。こうして産声をあげた競馬場で、記念すべき初めての開催が行われたのは昭和8年11月18日。東京競馬場の歴史はここに幕を開けます。
新たな競馬場の売り物といえば、広々としたコースと時代の先端をいく施設でした。平地競走用走路の1周距離は2100m、幅員30mと、他場の追随を許さないスケール。その内側には2本の調教用コースと全長3004mの障害コースも設けられました。一方の施設面に目を向ければ「東洋一の威容」と謳われた2つのスタンドのうち、1号館は地上4階建て、2号館は地上3階建て。2つのスタンドの中間から下見所に延びた大投票所には、電気、衛生、消火、排気、給水、暖房等の設備が完備されていました。また、1号館の中央部には7階建ての高さに相当する装飾塔があり、この白亜の尖塔は東京競馬場のシンボルとして親しまれたといいます。
新たな競馬場の売り物といえば、広々としたコースと時代の先端をいく施設でした。平地競走用走路の1周距離は2100m、幅員30mと、他場の追随を許さないスケール。その内側には2本の調教用コースと全長3004mの障害コースも設けられました。一方の施設面に目を向ければ「東洋一の威容」と謳われた2つのスタンドのうち、1号館は地上4階建て、2号館は地上3階建て。2つのスタンドの中間から下見所に延びた大投票所には、電気、衛生、消火、排気、給水、暖房等の設備が完備されていました。また、1号館の中央部には7階建ての高さに相当する装飾塔があり、この白亜の尖塔は東京競馬場のシンボルとして親しまれたといいます。

昭和12年 初代スタンド

初代スタンドと当時のパドック
ところが年々、戦時色が濃くなっていった時代背景のもと、オープンから3年後の昭和11年には改正競馬法が公布され、全国11の競馬倶楽部は国家が統制管理する「日本競馬会」に再編統合、いわゆる倶楽部競馬の時代は終わりを告げます。東京競馬倶楽部が高邁な理想を掲げて建設した東京競馬場も、倶楽部の解散にともなって日本競馬会の所有となり(昭和12年)、その後、戦局の激化による施設の一時閉鎖と陸軍施設への転用(昭和19年)、終戦後の開催再開(昭和21年)、国営競馬時代(昭和23~29年)、そして日本中央競馬会の創設(昭和29年)と時代は移り変わっていきます。しかし“主”は変われども、日本を代表する競馬場という位置づけは不変のまま、東京競馬場は歴史の針を刻んできました。思えば平成17年10月に天皇皇后両陛下の行幸啓を賜ったのも、“日本を代表する競馬場”であればこその栄誉といえます。
別項で触れるレースはもとより、施設面という観点からも、東京競馬場は日本の競馬界をリードする存在であり続けてきました。
別項で触れるレースはもとより、施設面という観点からも、東京競馬場は日本の競馬界をリードする存在であり続けてきました。

超大型マルチターフビジョン

全面ガラス張りのメモリアル60スタンド

平成19年 フジビュースタンド完成
日本の競馬場では初めてのダートコースが新設(昭和35年)されたのも、今ではすっかりお馴染みとなったターフビジョン(昭和59年より運用開始)、その改良機で当時のギネス認定も受けた超大型マルチターフビジョンが最初に設置(平成18年)されたのも東京競馬場でした。また、創設当初に建設された2つのスタンドは、その後、様々な変遷を経て、開設60周年を迎えた平成5年に竣工した「メモリアルスタンド」と平成19年にグランドオープンした「フジビュースタンド」に生まれ変わり、現在に至っています。
このうち、メインスタンドと位置づけられている「フジビュースタンド」(地上9階、地下1階)は、好天の日にはスタンドから富士山が遠望できること、「富士山=日本一」という連想、さらに富士山が世界的にも有名な山であることから、公募によりこの名前がつけられました。皇族のご来場も賜る、富士山を遠望できる唯一の競馬場、「馬の全能力が余すところなく発揮できる」広大なコースを擁し、日本の顔として親しまれてきた東京競馬場はこれからも、日本の代名詞でもある美しい山に見守られながら新たな歴史を積み重ねていくのです。
このうち、メインスタンドと位置づけられている「フジビュースタンド」(地上9階、地下1階)は、好天の日にはスタンドから富士山が遠望できること、「富士山=日本一」という連想、さらに富士山が世界的にも有名な山であることから、公募によりこの名前がつけられました。皇族のご来場も賜る、富士山を遠望できる唯一の競馬場、「馬の全能力が余すところなく発揮できる」広大なコースを擁し、日本の顔として親しまれてきた東京競馬場はこれからも、日本の代名詞でもある美しい山に見守られながら新たな歴史を積み重ねていくのです。
東京競馬場の沿革・その2(レース編)

東京競馬場を舞台に争われるGⅠレースは現在、年間に8競走を数えますが、なかでもとりわけの知名度を誇るレースといえば東京優駿、つまり日本ダービーを置いて他にありません。そして競馬の祭典とも呼ばれ、今では競馬サークルの枠組みを超えた広い層に親しまれているこのダービーの創設(目黒競馬場時代の昭和7年)は東京競馬場の建設に比肩する、東京競馬倶楽部が取り組んだ「もうひとつのビッグ・プロジェクト」と位置づけることができます。
競馬における競走体系の根幹が“3歳馬の5大クラシック競走”であることは世界の競馬界の通例です。様々な価値観が生まれ、一流馬が歩むローテーションも多様化した現在はともかく、ひとつの国の競馬が「世代毎のチャンピオンホースを決める」という分かりやすい競走体系とともに発展を遂げてきたことは歴史的な事実です。
競馬における競走体系の根幹が“3歳馬の5大クラシック競走”であることは世界の競馬界の通例です。様々な価値観が生まれ、一流馬が歩むローテーションも多様化した現在はともかく、ひとつの国の競馬が「世代毎のチャンピオンホースを決める」という分かりやすい競走体系とともに発展を遂げてきたことは歴史的な事実です。
近代式競馬が徐々に浸透しはじめ、大正12年の競馬法制定によって馬券の発売が正式に認可されて以降、競馬の人気がますます活況を帯びてきた頃の日本の競馬界でも、“柱”となるような競走体系を一刻も早く確立すべきだと考えている人は少なくありませんでした。なかにはそのものズバリ、「ダービーの創設」を訴える人もおり、元馬政官陸軍少将である石橋正人は大正12年、『馬の世界』という雑誌に「日本ダービーを創設せよ」というタイトルの論文を発表しています。「ダービーはイギリス競馬界の重要行事たるにとどまらず、実にその国民的年中行事」であり、「このダービーに倣って、各国競馬の主たるものには、皆ダービー競走が設けられている」ことを紹介したうえで、「競馬復興のこの機会において、本邦にもダービー競走の成立を希望せんと欲するものである」と提唱、ダービーの創設が日本の競馬界にもたらす波及効果の大きさや、セントレジャーやオークス、2000ギニー、1000ギニーに相当するレースを創設することの必要性にも言及したこの論文は、ダービーの創設に向けて投じられた重要な一石となりました。

昭和27年日本ダービー 8万人のファンを収容

昭和7年目黒競馬場で行われた第1回日本ダービー。記念すべき日本最初のダービー馬はワカタカであった
監督官庁である農林省もこの頃、馬産振興と育成技術向上のためには大レースの創設が不可欠と考え、“ダービーレースの編成”を検討しています。
しかし競馬法が制定されるまでの馬券発売禁止時代の間に生産界の体力は疲弊し切っており、当時はまだ、とてもダービーほどのレースを施行できる状況にはありませんでした。このように必要性と重要性は認識されながらも棚上げされてきたダービーの創設計画を具体化し、実現したのが東京競馬倶楽部の安田伊左衛門だったのです。
世界の競馬事情に通じており、早くからダービーを柱とする競走体系を確立することの必要性を痛感してきた氏は、競馬法制定以降の競馬人気の高まりと、これにともなって急速に活況を呈してきた生産界の状況を鑑みて機は熟したと判断、政府の了解をとりつけて昭和5年4月、1着賞金1万円(他に付加賞と価格1500円の金杯)という当時としては破格の“大賞金”を誇る競走を昭和7年春に施行することを世間に発表します。『東京優駿大競走編成趣意書』の中に記された有名な一文──ここに別記条件にもとづき東京優駿大競走を創設し、広く全国に良駿を求めて能力の厳選を試みむとす──からは、新たな歴史の扉をこれから開くという心の昂りがよく伝わってきます。
この発表は競馬関係者の間に大きな反響を巻き起こしました。付加賞を加えれば2万円にも及ぶという型破りな賞金額(従来の最高1着賞金額は連合農賞の6千円)は競走馬の価格の上昇を呼び、これによって生産界はますます活気付いたといいます。そして2年後の昭和7年4月24日、あいにくの雨をものともせず目黒競馬場へ押し寄せた約1万人の大観衆が見守るなか、いよいよ第一回のダービーが行われ、記念すべき初代の覇者にはワカタカが輝きました。
しかし競馬法が制定されるまでの馬券発売禁止時代の間に生産界の体力は疲弊し切っており、当時はまだ、とてもダービーほどのレースを施行できる状況にはありませんでした。このように必要性と重要性は認識されながらも棚上げされてきたダービーの創設計画を具体化し、実現したのが東京競馬倶楽部の安田伊左衛門だったのです。
世界の競馬事情に通じており、早くからダービーを柱とする競走体系を確立することの必要性を痛感してきた氏は、競馬法制定以降の競馬人気の高まりと、これにともなって急速に活況を呈してきた生産界の状況を鑑みて機は熟したと判断、政府の了解をとりつけて昭和5年4月、1着賞金1万円(他に付加賞と価格1500円の金杯)という当時としては破格の“大賞金”を誇る競走を昭和7年春に施行することを世間に発表します。『東京優駿大競走編成趣意書』の中に記された有名な一文──ここに別記条件にもとづき東京優駿大競走を創設し、広く全国に良駿を求めて能力の厳選を試みむとす──からは、新たな歴史の扉をこれから開くという心の昂りがよく伝わってきます。
この発表は競馬関係者の間に大きな反響を巻き起こしました。付加賞を加えれば2万円にも及ぶという型破りな賞金額(従来の最高1着賞金額は連合農賞の6千円)は競走馬の価格の上昇を呼び、これによって生産界はますます活気付いたといいます。そして2年後の昭和7年4月24日、あいにくの雨をものともせず目黒競馬場へ押し寄せた約1万人の大観衆が見守るなか、いよいよ第一回のダービーが行われ、記念すべき初代の覇者にはワカタカが輝きました。

昭和10年日本ダービー 優勝馬セントライト

平成17年日本ダービー 優勝馬ディープインパクト
昭和9年の第3回以降は東京競馬場に舞台を移し、戦争による開催休止(昭和20、21年)を挟んで現在にまで受け継がれてきたこのダービーからは、初代のセントライト、カリスマ的な人気を得たディープインパクトなどの三冠馬をはじめとする数々の名馬が誕生。先にも記した通り、競馬サークルの枠組みを超えた幅広い層から親しまれるレースに成長を遂げたダービーの創設が、日本の競馬のレベルアップと発展に大きく寄与したことは論を待ちません。
さて、世界の強豪に比肩する実力をつけた現在の日本の競走馬に多大な影響を及ぼしたレースといえばもうひとつ、昭和56年に創設されたわが国初の国際競走、ジャパンCも見逃すわけにはいきません。日本中央競馬会の内部で「海外の馬を招致してわが国初の国際レースを開催する」構想が、最初に浮上したのは昭和40年代の半ばでした。このときは時期尚早と見送られたものの、昭和50年代に入って「世界に通用する強い馬づくり」というスローガンが掲げられるようになると、先送りにされていた計画が再浮上。“強い馬づくり”のためには不可欠といえる国際競走の創設計画が実現に向けて動きはじめます。
さて、世界の強豪に比肩する実力をつけた現在の日本の競走馬に多大な影響を及ぼしたレースといえばもうひとつ、昭和56年に創設されたわが国初の国際競走、ジャパンCも見逃すわけにはいきません。日本中央競馬会の内部で「海外の馬を招致してわが国初の国際レースを開催する」構想が、最初に浮上したのは昭和40年代の半ばでした。このときは時期尚早と見送られたものの、昭和50年代に入って「世界に通用する強い馬づくり」というスローガンが掲げられるようになると、先送りにされていた計画が再浮上。“強い馬づくり”のためには不可欠といえる国際競走の創設計画が実現に向けて動きはじめます。
しかし何しろ前例のないこととあってその行く手には数々の困難が立ちはだかり、なかでも難航を極めたのが招待馬の誘致交渉でした。様々な紆余曲折を経て第一回のレースは昭和56年11月22日に行われることが決まり、同年9月に発表された計76頭の予備登録馬のなかにはジョンヘンリーをはじめとする当時のアメリカ競馬を代表するスターホースが名を連ねていましたが、それらのビッグネームはいざレースが近づくと次々に出走回避を表明。輸送距離の長さや検疫条件の厳しさ、またその頃、世界における日本の競馬の知名度がほとんど「ゼロ」に等しかったことを考えれば、大物のキャンセルが相次いだのも無理はありませんでした。

第1回ジャパンカップ優勝馬 メアジードーツ(米)
そうした状況のなか、第一回のレースに出走するために日本の地を踏んだ外国馬は8頭。このうち、トルコのデルシムが来日後に故障を発症したため、最終的にはアメリカ、カナダ、インドからの計7頭(ヨーロッパの馬が招待の対象に加えられたのは第二回以降)がゲートの中に収まります。全米最強牝馬という触れ込みのザベリワンを除けばほかの外国馬に特筆するほどの大物は見当たらず、対してこれを迎え撃つ日本馬は「オールスター・キャスト」と称されたほどの強豪揃いでした。それだけになおさら、第一回のレース結果は衝撃的なものとなりました。従来のレコードを一挙に1秒も短縮して鮮やかな差し切りを飾ったアメリカのメアジードーツをはじめ、4着までを外国馬が独占。一方の日本馬はゴールドスペンサーの5着が最高着順だったのです。
しかしこの衝撃的な完敗をきっかけに日本の競馬界では“強い馬づくり”に本腰を入れて取り組む機運が一気に高まり、以降の日本馬は急速に力をつけていきます。第一回のレース後には「日本の人馬は今世紀中にこのレースを勝てるのだろうか?」という悲観論さえささやかれたのが嘘のように、2年後に行われた第三回のレースでは秋の天皇賞馬キョウエイプロミスがゴールの直前に故障を発症しながらも優勝したスタネーラ(アイルランド)にアタマ差の2着と迫り、第4回のレースではカツラギエースが日本馬によるジャパンC初制覇を達成。さらに翌年には皇帝と呼ばれたシンボリルドルフが1番人気の支持に応えて堂々の戴冠を果たしました。創設当初の力関係はすっかり逆転し、近年は圧倒的な優勢を日本馬が築いていることはご存知の通りです。
今や世界的な知名度を誇るようになった「Tokyo Racecourse」と日本馬の実力。短期間のうちに日本の競馬界が遂げた長足の進歩の出発点となったジャパンCの創設は、日本の競馬史における重要なターニングポイントのひとつと記憶されているのです。
今や世界的な知名度を誇るようになった「Tokyo Racecourse」と日本馬の実力。短期間のうちに日本の競馬界が遂げた長足の進歩の出発点となったジャパンCの創設は、日本の競馬史における重要なターニングポイントのひとつと記憶されているのです。